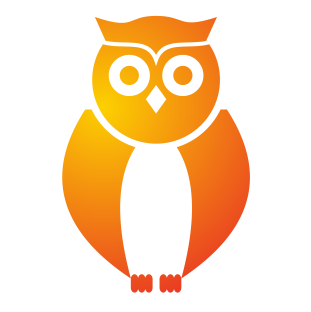Lien Protocol ( コールオプションを用いた暗号通貨デリバティブ型ステーブルコイン) の仕組みと課題
2020年4月1日、暗号通貨を担保にするのではなくそのデリバティブを用いたいわば暗号通貨デリバティブ型とも呼べる新しいタイプの、ステーブルコインの生成メカニズムであるLien protocolとよばれるプロジェクトが発表されました。
Lien には大きく次の2つの特徴があります。
- 暗号資産が担保なのにも関わらず過剰な担保が必要ない
- すべてのプロセスがプロトコルと市場原理に基づいて設計されておりガバナンスが存在しないため仕組みがシンプル
こうした特徴により、Lienを使うことで、 従来の暗号通貨担保型のステーブルコインよりも頑健で簡潔な方法で、ETHを担保にしたステーブルコインを効率よく作ることを可能になります。
本記事では、Lienのメカニズムと特徴ほかのステーブルコインとの比較について解説していこうと思います。
目次
暗号通貨担保型ステーブルコインの問題点とは
Lienは何を解決したか
Lienの概要
- プロセスの全体図
- LBTとSBTの生成と特徴
- iDOLの生成
Lienの課題
結論
暗号通貨担保型ステーブルコインの問題点とは
従来の暗号通貨担保型のステーブルコインには2つの欠点があります。(ステーブルコインについてはこちらの説明をご覧ください)
1. 担保に対する暗号通貨担保型ステーブルコインの発行率が低い
2. 多くの人にとってステーブルコインを発行するメリットがない
の2つです。
担保に対する暗号通貨担保型ステーブルコインの発行率が低い
まず、担保に対するステーブルコインの発行率が低いことについてです。
暗号通貨担保型ステーブルコインはその価値の裏付けに同額以上の担保が存在している必要があります。
なぜなら、担保(ETHなど)の価格が下落してもステーブルコインの価値を法定通貨と同一に保てるようにする必要があからです。
なので担保の金額に対して生成するステーブルコインの発行額に余裕を持たせる必要があります。
例えば、MakerDAOと言うプロジェクトで発行できるDAIと呼ばれる暗号通貨担保型ステーブルコインはドル建てで担保の66%しか発行できない仕組みになっています。
これではこの先、イーサリアムやコスモスなどの経済圏が発展した時に必要な分の暗号通貨担保型ステーブルコインを発行できない可能性があり、需要が増大した場合価格の安定性を損なう可能性があります。
- 多くの人にとってステーブルコインを発行するメリットがない
次に、そもそも多くの人にとって暗号通貨担保型ステーブルコインを発行するメリットがないというのが挙げられます。
暗号通貨担保型ステーブルコインでは、価格下落リスクの他に、ETHを担保してDAIを発行し続けている間DAIの価格を1ドルに保ち続けるための手数料を払い続けなければなりません。
この手数料のことをステーブルフィーと言います。
DAIの供給量が過剰な場合はステーブルフィーを上昇させてDAIの精算を促し、逆にDAIの供給量が不足している場合はステーブルフィーを下落させ発行を促します。
つまり、DAIはステーブルフィーを上下させて価格を安定させる仕組みをとっています。
しかし、ステーブルフィーは現状0%以下にはならないので、DAIを生成するためにユーザーはステーブルフィーを支払わなければなりません。
例えば、ステーブルフィーが5%の状態で100DAIを発行した場合、1年の間発行したら、返却してETHを引き出すときには105DAI相当を返さないといけないということです。
つまりDAIの発行者には以下のようなリターンとリスクがあります。
| メリット | デメリット |
| ・暗号通貨を利確せずにステーブルコインを保有して価格上昇にかけることができる | ・DAIを発行している間に発生し続けるステーブルフィー
・ETHの価格下落リスク |
そのため、ステーブルフィー(例えば5%など)よりも高い割合でETHの価格が上昇しなければ損をしてしまうためそれを信じることができる人しかDAIを発行することはありません。
また、ステーブルフィーを0%以下にするためにはシステム全体をアップグレードしなければなりません。
上記のような2つの問題により、暗号通貨担保型ステーブルコインは発行者にとっても利用者にとっても利用しやすい仕組みではありません。
Lienは何を解決したか
Lienでは、暗号通貨ではなく、暗号通貨で作った金融商品である暗号通貨デリバティブを担保にステーブルコインを生成することで、以下の2つの課題を解決しようとしています。
- 過剰担保による暗号通貨担保型ステーブルコイン発行効率の低下
- ステーブルフィーによる暗号通貨担保型ステーブルコイン発行意欲の減退
これにより、Lienは暗号通貨担保型のDAIと比べてステーブルコインの供給量の増加と価格のより一層の安定を期待することができます。
以下ではLien全体の仕組みと登場する構成要素の役割について解説していきます。
Lienの概要
- プロセスの全体図
まず、Lienのプロセスの次の図のようになります。
全体のプロセス
iDOL White Paper Lien Protocol より転載
Lienの各プロセスについて解説します。
1. ETHを担保しLBT(コールオプションの役割を担うトークン)とSBT(LBTに対して1:1で生成されるトークン)を発行する
- SBTとLBTをそれぞれリスクをヘッジしたい人とリスクを取りたい人に売る
- LBTはマーケットによって自由に売買される。SBTをロックすることによってiDOLが生成される
- iDOLはステーブルコインとして自由に流通する
- LBTとSBTの生成と特徴
Lienでは担保にしたETHの量に応じてステーブルコイン( iDOL) が生成されるため、担保にするETHの量を最初に決める必要があります。
この時、担保にしたETHがどれだけの価格下落までステーブルでいられるかの割ってはいけない時価総額 (K1 とする) も同時に決めます。
このK1の時のETHの単価のことをPEG価格と言います。
例えば、1ETH=100ドルの時に10ETH分(1000ドル相当のETH )を担保にして1000ドル相当のiDOL を発行するとき、K1を500ドルに設定します。そうすると単価であるPEG価格は50ドルになります。
次のようにして、満期が来たら必ず償還しなければならない有効期限の決まっている2種類の暗号通貨デリバディブトークンを生成するところからスタートします。
(ホワイトペーパーには書かれていませんが、満期期間も自分で指定する設計のようです)
生成される2種類のトークンは
SBT:オレンジの点線の高さで示された時価総額K1の下にある黒斜線で示された部分➀
(先ほどの例だと1ETH50ドル×1ETHの部分)を受け取るための引換券であるステーブルコインのような性質を持つ)
LBT:SBTより上の赤斜線で示された部分➁
(先ほどの例だと1ETH=100ドルから1ETH=150ドルになった場合(150-50)×1ETH)を受け取るための引換券であるコールオプションのような性質を持つ)
の2つです。
金融広報委員会 知るぽるとより転載
コールオプションとは、手数料を支払い、(図の水色の直線部分)ある行使価格(決められている価格の権利)でその商品を買う”権利”のことです。この手数料はオプションプレミアムと呼ばれます。
LBTの買い手はコールオプションの買い手のことを指すので、以下のコールオプションの説明は水色の線の部分のことを指します。
仮に1ヵ月後1ETH=100ドルで買う権利”を買ったとして、満期時に200ドルになっていたら、100ドルで買うことができるので、その瞬間に100ドルの利益が発生します。
逆にもし買うタイミングで行使価格を下回ったら”権利”を放棄することができます。
なので、損失の最大金額は、初めからオプションプレミアムに限定されているのが特徴です。
また、このような債権と金融商品を組み合わせた商品を仕組債と呼びます。
例えば、”日経平均株価が満期までに1万8000円を割らなければ2%の金利をもらえそうでなければ15%元本が差し引かれる”など商品の価格に連動した債権のことを言います。
SBTの特徴
X軸が価格、y軸が時価総額
iDOL White Paper Lien Protocol より転載
SBTは上の図では黒斜線の部分➀の時価総額を表します。
例えば、1ETH=100ドルの時に100ドル分、満期が7日、PEG価格=50ドルで担保したとします。
7日以内に1ETHの価格が半値を割っている可能性は極めて低いため半値分のETHの引換券であるSBTもまた、とほぼ同じ価値を持ちます。
先ほどの例ならば、現在1ETH=100ドルで割っちゃいけないステーブルを維持できる価格が1ETH=50ドルのため、仮にSBTの価格が45ドルまで下がった場合、買い手から見たら50ドル受け取れるものが45ドルで売っていることになります。
そのため、このSBTを買えばほぼ確実に儲かるので買い注文が発生し、価格が自動的に市場原理で是正される仕組みとなっています。
ただし、SBTは担保したETHの価格が上昇してもそのぶんの価格上昇の恩恵は受けられず、担保した分のETHのドル建て価格しか受け取れない仕組みとなっています。
LBTの特徴
X軸が価格、y軸が時価総額
iDOL White Paper Lien Protocol より転載
LBTは上の図では赤斜線の部分➁の時価総額を表します。
LBTの方は前述したコールオプションなので、担保を提供することなく最初のオプションプレミアムの手数料だけで価格の上昇にかけることができます。
また、仮に価格が下落した場合でも権利を放棄すればいいので、損失は最大もオプションプレミアムの支払いだけに限定されており、追証も発生しません。
PEG価格が下回った場合のLBTの価値はゼロですが、価格が上昇していた場合その分の利益をまるまる受け取ることができます。
Lienの肝は、このように担保である1種類の資産(ETH)から役割の違う2種類の分離した資産(SBTとLBT)を作り、お互いを補い合うことにあります
- SBTとLBTをそれぞれリスクをヘッジしたい人とリスクを取りたい人に売る
このようにして、LBTとSBTを生成した人は、LBTに手数料をつけて売り払うことによって利益を上げることができます。
LBTはETHの価格上昇にかけたい人がそれぞれ買い手となります。
- LBTはマーケットによって自由に売買される。SBTをロックすることによってiDOLが生成される
LBTは、マーケットに上場にしてLBTの値上がり益が欲しい投機家によって売買されます。
SBTは、それを担保することにすることでiDOLが生成されます。
iDOLは、様々な満期やPEG価格のSBTを集めてSBTより満期保証を高めたステーブルコインです。
LBTとSBTを発行した人は、SBTをそのまま保有しておくよりも様々なSBTの集合体であるiDOLにしておいた方が安全性が高いのでSBTを担保にするインセンティブが働きます。
- iDOLはステーブルコインとして自由に流通する
iDOLも、LBTと同じようにマーケットに上場しステーブルコインが欲しい人によって、自由に売買させます。
Lienの課題
Lienには、”コールオプションであるLBTの買い手が現れなけれはSBTを発行できない”という性質があります。
LBTはETHのコールオプションの役割がありますが、他の取引所でも同じような設計のコールオプションを発行しています。
なので、LBTが類似商品との競争に負けてしまいLBTの買い手がつかなければ対になって生成されるSBTも発行することができません。
そのため、LBTは常に他の類似製品と競争にさらされており一定以上の需要を拡大し続けなければ発行料を拡大することができません。
また、満期が長いSBTや単価であるPEG価格までの価格幅が短いSBTなど、満額に帰ってくる可能性が十分なSBTをiDOLにロックする時にどうするのかなども決まっていません。
最後に、ETHの価格が急落して、iDOLから引き出せる金額が満額保証ができなかった時に、どのような振る舞いをするのかが不透明で、ホワイトペーパーでも明確に書かれていません。
結論
Lienは、今までにない新しい概念でMakerDAOの重要な課題を解決しているのは非常にユニークだと思います。
その一方、現状ではiDOLの精算の話など細かい部分の具体的なパラメータが全く決まっておらず、仕組みそのものがどう働くのか非常に不透明な部分が多くあります。
今後、具体的な話が出てきたら注目も高まってくると思うので今後要注目です。
参考文献
https://medium.com/lien-finance/lien-a-new-crypto-backed-stable-coin-without-over-collateralization-6a145d8fb4a4
https://lien.finance/pdf/iDOLWP_v1.pdf
https://lien.finance/
https://www.shiruporuto.jp/public/data/encyclopedia/deriv/deriv304.html